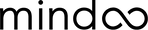「掃除を時短で行いたい」「負担を減らせる掃除道具が知りたい」とお悩みの方は、多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、それらのお悩みを抱えた方に向けて、おすすめの掃除道具や効率よく掃除する裏技を紹介します。
家を常にキレイな状態で保ちたい方や、掃除を簡単に済ませる方法を知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。
掃除をする前に考えておきたいこと

いきなり掃除に取りかかる前に、考えておくべきことがあります。
お部屋の広さや、自分のライフスタイルに合わせて、無理のない範囲でキレイな状態を維持しましょう。
掃除場所を決める
掃除する際は、1日で家の中すべてをキレイにしようと思わないことが大切です。
まずは、“キッチンシンクだけ”“トイレだけ”といったように、範囲を決めて掃除しましょう。
どこから掃除すればよいのかわからないという方は、目についた箇所からキレイにしていく方法がおすすめです。
特に手間がかからない場所から始め、徐々に範囲を広げていけば負担が少ないため、モチベーションを維持できます。
掃除頻度を決める
一人暮らしや共働きの家庭など、ライフスタイルの違いによって理想の掃除頻度は変わります。
一人暮らしの場合は、掃除機がけなどの簡単な掃除を2~3日に1回は行いましょう。
休日は水回りを含めて家全体を掃除すると、キレイな状態が維持できます。
共働きの方は、平日にまとまった時間を確保するのが難しいため、普段は無理のない範囲で簡単に掃除し、休日に部屋全体をしっかりとキレイにしてください。
パートナーと役割を分担することで、お互いの負担を減らせます。
関連記事:掃除の頻度はどれくらいが理想?最適な頻度とポイントを紹介
場所別の掃除方法とポイント

ここからは、リビングや寝室、キッチンなど、場所ごとの掃除方法を解説します。
それぞれの所要時間や掃除頻度の目安など、掃除するうえで知っておきたいポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
リビング
- 所要時間:5分~
- 掃除頻度の目安:毎日(時間に余裕がないときは週2~3回)
リビングは家族の出入りがもっとも激しいため、ホコリや髪の毛などのごみが舞いやすい場所です。
時間に余裕があるときは毎日、忙しいときは週2~3日の頻度で掃除機をかけましょう。
掃除するときは、最初に散らかっているものを片付けます。
日頃から整理整頓を心がけていると、ものが散らからないため、片付ける手間が省け、掃除の時短につながります。
掃除機をかけたあとは、床全体の水拭きを行いましょう。
吸い込みきれなかった小さなホコリや、皮脂汚れなどを拭き取ることができます。
乳児など小さなお子さまやペットがいるご家庭は、リビングで過ごす時間が長いため、こまめな掃除が必要です。
関連記事:フローリングの正しい掃除方法は?素材や汚れ別に紹介
寝室
- 所要時間:5分~
- 掃除頻度の目安:週2~3回
寝室は布製品が多いため、床にホコリや髪の毛などがたまりやすくなります。
毎日出入りするものの、リビングほど頻繁に行き来するわけではないため、週2~3回ほどの掃除で十分です。
寝室を掃除する際、ベッド下のホコリや髪の毛もしっかり取り除きましょう。
布団やシーツの上に残っている髪の毛を取り除くときは、粘着クリーナーを使うと時短につながります。
また、換気しながら掃除することで、カビやダニの繁殖を抑制できます。
布製品の「汚れが気になるけれど洗えない」そんなお悩みにはMindoo PureXもございます。
コンパクトな見た目からは想像できないほどパワフルに、布製品の汚れをすっきりきれいにしてくれるコードレスウォータークリーナーです。
Mindoo PureXについてはこちらから詳細をご確認下さい。
キッチン
- 所要時間:15分~
- 掃除頻度の目安:毎日
キッチンには主に、調理をするときに発生する油汚れや、食器を洗うときに出る水垢やぬめり、カビなどの汚れがあります。
これらの汚れは重曹とクエン酸で、簡単に落とすことができます。
コンロの油汚れには、重曹を含むアルカリ性洗剤が有効です。
コンロには油が付着しやすいので、分解して掃除しましょう。
特に洗いにくい形状の五徳は、重曹でつけ置き洗いすると汚れが落ちやすくなります。
白い汚れが浮いてきたあとに、歯ブラシなどで気になる部分を削ってください。
クエン酸は、シンクの排水溝のぬめりや水垢を取り除いてくれます。
水垢の原因であるミネラルはアルカリ性なので、酸性のクエン酸で落とす方法が効果的です。
シンクは1日の最後にスポンジで水洗いし、そのあとに残った水滴を拭き取りましょう。
2週間に1回程度、クエン酸を使って掃除するとキレイな状態を維持できます。
トイレ
- 所要時間:5分~
- 掃除頻度の目安:便座や便器は毎日、壁や床は週に1回程度
トイレは便座や便器にはもちろん、床や壁にも汚れが付着しています。
便器内は、市販のトイレ用中性洗剤を吹きかけ、トイレブラシで洗いましょう。
近年は、ブラシが不要の中性洗剤も多く販売されています。
便器やトイレタンクの外側、便座は、トイレ掃除用のウェットシートで拭いてください。
床や壁の拭き掃除は週に1回、アルコール除菌タイプのウェットシートで掃除しましょう。
定期的に拭き掃除を行うことで、気になるニオイを抑制できます。
浴室
- 所要時間:5分~
- 掃除頻度の目安:毎日
湿気でカビが繁殖しやすい浴室の掃除は、毎日行うことをおすすめします。
スポンジと重曹を使って皮脂汚れを落とし、排水溝にたまった髪の毛を取り除きましょう。
壁やゴムパッキンなどを含む全体的な掃除は、週に1回が目安です。
重曹で汚れを落としたあとに、シャワーで洗い流してください。
壁に残った水滴はカビの繁殖につながるため、最後にスクイージーをかけて水切りするのも忘れてはいけません。
浴室を掃除する際に使用する塩素系の漂白剤と酸性タイプの洗剤は、混ざると危険な塩素ガスが発生するため、取り扱う際は注意が必要です。
また、塩素系の漂白剤は独特なニオイを発生させるため、浴室を換気しながら使用してください。
洗面台
- 所要時間:5分
- 掃除頻度の目安:毎日
洗面台の汚れは、水に含まれるカルシウムが固まってできる水垢や石鹸カス、皮脂汚れなどが原因です。
その状態を放置していると、洗面台に黒ずみやカビが発生します。
洗面台の黒ずみやカビ、水垢はクエン酸を使用することでキレイに落とすことができます。
メラミンフォームのスポンジは、気になる箇所を軽く擦るだけで汚れが簡単に落ちます。
ただし、素材によっては洗面台に傷がつくため、使用する際は事前に確認しましょう。
床に落ちた髪の毛やホコリも忘れずに取り除き、残った小さなごみは雑巾などで水拭きすることで、さらにキレイになります。
玄関
- 所要時間:5分~
- 掃除頻度の目安:掃き掃除は週に1回、拭き掃除は月に1~2回
外とつながっている玄関は、砂やホコリ、花粉などで汚れやすい場所です。
週に1回はほうきで掃き掃除を行い、月に1~2回は雑巾で拭き掃除を行ってください。
泥汚れは、乾くとなかなか落ちにくいため、濡れているあいだに雑巾でサッと拭きとりましょう。
また、靴箱は湿気がこもりやすく、掃除せずに放置したままにすると、嫌なニオイが発生します。
定期的に拭き掃除をしたり、靴を天日干しにしたりすることで、ニオイの発生を抑えることが可能です。
掃除が楽になるおすすめの掃除道具

便利な掃除道具を活用するのも、掃除を簡単にするための大切なポイントです。
雑巾や洗剤、メラミンスポンジなどを活用して、キレイな状態を維持しましょう。
雑巾・軍手・ストッキング
拭き掃除をする際は、雑巾や軍手、ストッキングを活用するのがおすすめです。
これらは掃除機のように大きな音を立てることがほとんどないため、乳児がいるご家庭でも静かに掃除できます。
雑巾は、床や窓を掃除するのに適しています。
場所によって雑巾の素材を使い分けることで、より効果的に掃除することが可能です。
軍手は、雑巾では掃除しにくい細かい部分に最適です。
電子機器のコード周りや、ブラインドのホコリを効率よく取り除けます。
ストッキングは化学繊維で作られており、肌になじむようなやわらかい手触りが特徴です。
そのため、家具を傷つけずにごみを絡め取ってくれます。
ホコリを取るだけでなく、排水口の髪の毛や生ごみを集めるネットとして活躍してくれるのも、ストッキングの魅力です。
洗剤
洗剤は、家の掃除をさらに楽にするアイテムです。
掃除用洗剤として人気の重曹やクエン酸、セスキは、水に溶かして使用します。
いずれも比較的手頃な価格で購入できるうえに、粉末タイプのものは自分好みに濃度を変えることができます。
洗剤によって得意とする汚れが異なるため、状況に合わせて適切なものを選びましょう。
洗剤の特徴
| 重曹 | クエン酸 | セスキ | |
| 性質 | 炭酸水素ナトリウム | 酸性 | アルカリ性 |
| 得意な汚れ | ・油汚れ ・皮脂汚れ ・焦げ落とし など |
・水垢 ・石鹸カス ・アンモニアの汚れ など |
・赤カビ対策 ・黒カビ対策 ・油汚れ ・皮脂汚れ など |
| 苦手な汚れ | ・水垢 ・カルキ など |
・油汚れ ・油脂の汚れ など |
・泥汚れ ・衣類のシミ など |
| 保存方法 | ・直射日光、高温、多湿を避ける ・アルミ製以外の蓋つきの容器に保存する |
・直射日光、高温、多湿を避ける ・金属製以外の蓋つきの容器に保存する |
・直射日光、高温、多湿を避ける ・蓋つきの容器に保存する |
| 注意点 | ・湿気を含むと固まりやすくなる ・アルミに触れると黒ずむことがある |
・大理石やセメントに触れると溶けることがある ・金属に触れると錆びることがある ・塩素系と混ぜると有毒ガスが発生する場合がある |
・湿気を含むと固まることがある |
使用する場所によっては、家具などにダメージを与えるおそれがあるため、注意が必要です。
メラミンスポンジ
メラミンスポンジは、汚れを簡単に落とせる便利なアイテムです。
水に濡らして擦るだけでも十分効果を発揮しますが、洗剤と組み合わせて使用すれば、なかなか落ちない頑固な汚れもキレイに消し去ることができます。
ただし、くもり止め加工が施された鏡や、コーティングされたフローリングに使用すると、表面の加工剤が剥がれるおそれがあるため、使用は控えてください。
力加減に気をつけたり、適した素材に使用したりすれば、汚れをキレイに落とせます。
食品用ラップ・キッチンペーパー
食事を保存するときに使用する食品用ラップや、キッチン周りで使用するキッチンペーパーは、掃除道具としても活躍します。
本来、壁や鏡などの、縦になっている部分にかけた洗剤は垂れてきてしまいますが、ラップやキッチンペーパーを上から貼れば、定着させることができます。
また、食品用ラップとキッチンペーパーは、浴室のカビ退治にも効果的です。
カビを取り除きたい部分にキッチンペーパーを当て、上からカビ取り用の洗剤を吹きかけます。
ラップで密閉し、20分ほど放置すると、カビをキレイに落とせます。
最旬の乾湿両用の水拭き掃除機

Mindooの『AquaX(アクアエックス)』は、“吸引”と“水拭き”が同時に行えるため、掃除時間の大幅な短縮につながる、画期的な掃除機です。
また、99.9%除菌もできるので、お子様やペットのためにもおすすめです。
ヘッドの先端部分は、高密度ポリエステル化学繊維ロールブラシを採用しています。
1分間に540回転するロールブラシの摩擦力で、頑固な油汚れや皮脂汚れも逃がしません。
掃除後は専用の充電スタンドにもどしてセルフクリーニングボタンを押下するだけで、ブラシと本体内部の洗浄を自動で行ってくれます。
『AquaX』の実際の使用感は以下の記事でご紹介しています。
Mindooの水拭き掃除機『AquaX』の使用感をレビュー!【実際に使ってみた】
Mindoo AquaX(アクアエックス)の特徴
| 水拭き | 〇(吸引同時) |
| 吸引のみ | 〇 |
| スチーム | × |
| 自動モップ洗浄 | 〇 |
| 自動モップ乾燥 | × |
| 水タンク容量 | 給水420ml、排水500ml |
| サイズ (幅×奥行×高さcm) | 28×26.8×109.9 |
| 重さ | 3.8kg |
| 洗剤自動投入 | × |
| 汚れ検知 | × |
| 液晶ディスプレイ | 〇 |
| スマホアプリ | × |
| 汚れ検知 | × |
| 最大稼働時間 | 35分 |
| 販売価格 |
54,800円(税込) ※本コラム作成時の価格です。 |
高機能で軽量設計の掃除機を探している方や、掃除後のお手入れの時間を短縮させたい方にはぴったりの商品です。
関連記事:水拭き掃除機の種類や選び方を詳しく紹介
掃除の負担を減らすコツ

掃除の負担を減らすために、日々の生活でルールを決めておくのも大切です。
ここからは、ものが散らからないようにするためのコツを紹介します。
ものの位置を決める
まずは、ものの位置を決めましょう。
家の中が散らかるのは、ものの定位置が普段から決まっていないことが原因です。
ものの位置をあらかじめ決めておくことで整理整頓でき、片付けが苦手な方でも普段からキレイな状態を維持できます。
床や机にものを置かない
床や机にものを置きっぱなしにすることは、掃除をする際の負担につながります。
掃除をスムーズに行うために、普段から床や机の上になるべくものを置かないようにしましょう。
ものが散らばった状態だと、掃除するたびにそれらを直さなくてはいけないので、無駄な時間が発生します。
掃除時間を短縮するためにも、普段から床や机の上にものを置かないことが大切です。
掃除道具を取り出しやすくする
掃除しようと思い立っても、掃除道具が取り出しにくいと、それだけでやる気が削がれてしまいます。
毎日使用する掃除道具は取り出しやすく、片付けやすい場所に収納しましょう。
頻繁に掃除する習慣を身につけるためには、掃除道具を取り出しやすい場所に収納することが大切です。
ながら掃除をする
仕事のある平日は、掃除になかなか時間を割くことができません。
そんなときは、何かのついでにちゃちゃっとできる、“ながら掃除”がおすすめです。
たとえば、トイレのついでに便座や床をサッと拭いたり、お風呂のついでに浴槽を洗ったりするだけで、日頃の掃除の負担を減らすことができます。
簡単にできる掃除の裏技

場所ごとに異なる頑固な汚れは、裏技を活用することで、簡単にキレイにできます。
ここからは、コンロの油汚れや網戸など、汚れがつきやすい場所の掃除方法を紹介します。
頑固な油汚れは温める
キッチンでほぼ毎日使用するコンロは、油汚れがつきやすく、一度固まった汚れはなかなか落とすことができません。
重曹で擦っても十分に落ちるのですが、その前にお湯に浸けることで、さらに簡単に汚れを取り除くことが可能です。
固くなった油汚れは温めることでやわらかくなって、落としやすくなります。
特に頑固な汚れがつきやすい五徳は、60℃ほどのお湯に小さじ1杯の重曹を入れ、その中に1時間ほど浸けると、汚れを簡単に落とすことができます。
カーペットやソファー掃除はゴム手袋を使う
カーペットやソファーに絡みついた髪の毛は奥のほうまで入り込んでしまい、掃除機で吸い込んでもなかなか取ることができません。
そんなときは、ゴム手袋を使用しましょう。
ゴム手袋を装着してカーペットやソファーを撫でるだけで、ホコリや髪の毛がくるくるとまとまります。
手を伸ばせば、粘着クリーナーではなかなか奥まで行き届かないソファーのすき間も、掃除することができます。
掃除が終わったあとは、ゴム手袋をそのまま捨てればよいだけなので、片付けも簡単です。
網戸の掃除は雨の日に行う
網戸を掃除するのに適しているのは、“湿気の多い雨の日”です。
網戸についている小さなごみは、湿気を含むことでまとまりやすくなり、室内に散らばるのを防いでくれます。
ホコリを落とすときは、ハケや歯ブラシなどで払い落としましょう。
その後、雑巾2枚で網戸を挟み込むようにして拭くと、ごみが散らばることなくまとまります。
それでも落ちない頑固な汚れがあった場合は、メラミンスポンジで擦ると簡単に落ちます。
メラミンスポンジの細かい網目が、小さなごみを絡め取ってくれるのです。
シンクのぬめりはアルミホイルで対策する
シンクのぬめりには、排水溝に丸めたアルミホイルを入れておくのが効果的です。
アルミホイルは、濡れると細菌やバクテリアの繁殖を防ぐアルミニウムイオンを発生させます。
そのアルミニウムイオンにある殺菌作用が、排水溝の雑菌が繁殖することを防ぎ、ぬめりの抑制につながります。
掃除を効率よく行うには、日頃の整理整頓が大切

本記事では、掃除方法のポイントや裏技を解説しました。
きちんと掃除しようと思うと、どうしても時間がかかってしまうものですが、日頃からの整理整頓や、時短のコツをつかむことで負担を減らすことができます。
掃除は定期的に行うことが大切です。
一人暮らしの場合は1週間に2~3回程度、共働きの方は、平日は無理のない範囲で掃除しましょう。
Mindooでは、今回紹介した『AquaX(アクアエックス)』や、掃除の負担を減らすコードレスファブリッククリーナー『PureX(ピュアエックス)』を販売しています。
AquaXは吸引と水拭きを一度で行ってくれるため、従来の掃除よりもおよそ75%の時間を短縮できます。
掃除時間を短縮したい方や、平日は掃除になかなか時間がとれない方はぜひお求めください。