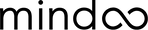畳に掃除機をかける正しい方法とは?傷めないコツやおすすめ掃除機まで徹底解説
畳は和室の心地よさを支える素材ですが、扱いを誤ると表面が毛羽立ち、色むらやへこみの原因になります。とくに掃除機は便利な一方で、方向・吸引力・ヘッド選びを間違えると畳表を傷めるため、注意が必要です。 本記事では、避けたいNG行動を整理し、畳の目に沿った動かし方などを解説します。 さらに、初心者にも実践しやすいチェックリストを用意しました。掃除後の乾拭きと換気で湿気を残さないポイントなどを知りたい方はぜひご覧ください。 [aquax-plus1] 畳に掃除機をかけるときのNG行動とは? 畳はデリケートな素材のため、やり方を誤ると寿命を縮めます。見落としがちなNG行動を理解しておくことが、正しい掃除への第一歩です。 畳の目の向きと反対にかける 強すぎる吸引力や高速ブラシを使う ゴシゴシ往復してこすりすぎる 湿気が残る状態で放置する これらを避けることで、畳の表面を守りながら清潔に保てます。それぞれの行動がなぜNGなのかを具体的に見ていきましょう。 畳の目の向きと反対にかける 畳は天然のい草を一定の方向に編み込んで作られているため、この編み込みの方向(畳の目)と逆方向に掃除機をかけると、い草を傷つける原因となります。 目に逆らって掃除機をかけることで、い草が擦り減り、ささくれや毛羽立ちが発生しやすくなるのです。また、畳の目に逆らった掃除は細かなゴミを畳の奥深くに押し込んでしまい、反対に汚れが取りにくくなることもあるでしょう。 さらに、掃除機のローラー部分が畳表面を何度もこすることになり、摩擦によるダメージが蓄積されていきます。このような掃除方法を続けていると、畳の表面が次第に劣化し、快適な和室環境を損ないます。 強すぎる吸引力や高速ブラシを使う 掃除機の吸引力を最大設定にしたり、高速回転するブラシを使用したりすることは、畳にとって大きな負担です。強すぎる吸引力は、畳表面のい草を無理やり引っ張ってしまい、ささくれや抜けを引き起こす原因となります。 パワーブラシなどの回転ブラシは、カーペット用に開発されたものであり、繊細な畳には不向きです。畳掃除の際は、吸引力を弱から中程度に設定し、ブラシ機能は基本的にオフにするか、ソフトブラシに切り替えましょう。 また、掃除機のたたき出し機能は使用してはいけません。この機能は畳のい草に大きなダメージを与え、表面を著しく傷つける可能性があります。畳専用モードや和室モードが搭載された掃除機を使用することで、適切な吸引力で安全に掃除できるでしょう。 ゴシゴシ往復してこすりすぎる...